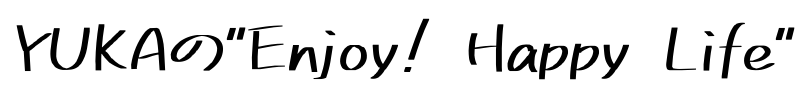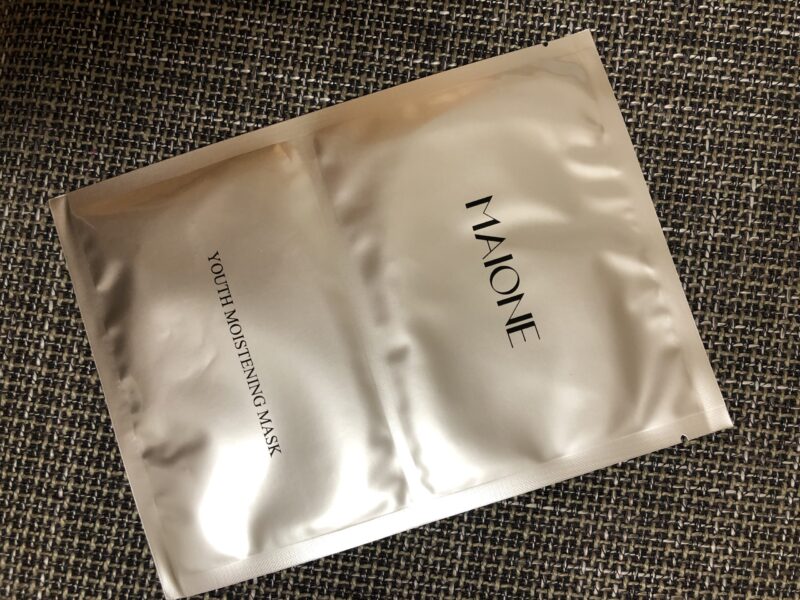今は専業主婦の私ですが、フルタイムでバリバリ仕事をしている頃は常に「疲労感」を抱えていました。
とにかく体が重くてだるいのです。
せっかくの休日も、あまりのだるさに「外出したくない」と思うことが多かったです。
「ショッピングに行きたい!」「テーマパークで遊びたい!」という気持ちがあっても、ひたすら歩いたり行列に並んだりする自分の姿が思い浮かび、「疲れが増すだけだ・・・」と嫌になっていました。
少しでも「体の疲れ」を癒そうと、定期的にマッサージやエステに行っていました。
ところが、最新の研究で「体の疲れ」の正体・メカニズムが明らかになり、なんと「疲労=体が疲れているわけではない」ということがわかってきました。
長年「乳酸が疲労の原因である」と言われてきましたが、これは事実ではないそうです。
確かに、無酸素運動をすると筋肉に乳酸が溜まりますが、体には必要な現象です。
乳酸は筋肉を修復する役割があり、脳の栄養源にもなるからです。
「体が疲れた」と感じている人の大半が、実は「脳が疲れている」そうです。
体ではなく、脳の司令塔である自律神経が疲れていて、それが「疲れ」「疲労感」となって体に現れてきます。
自律神経には交感神経(活動・緊張)と副交感神経(休息・リラックス)の2種類が存在し、体の機能を調節する働きがあります。
心拍・血流・呼吸などをコントロールして生命を維持する重要な神経です。
多くの人が感じる体の疲れは、この自律神経の疲れが原因なのです。
例えば、3キロのウォーキングをする時、春の気持ち良い気候の中で歩くのと、真夏の炎天下で歩くのとでは、疲労度が異なります。
歩く距離は同じなので、筋肉や内臓の負担は変わらないはずなのに、なぜか疲労度に違いが出てきます。
真夏の炎天下で運動すると、自律神経が体温調節をするために汗をかいたり、呼吸数を増やして呼気から熱を出したりするよう命令を出します。
生命を維持するために自律神経がフル稼働している状態です。
そのような時、つまり自律神経が疲れた時に、人は「体が疲れた」と感じさせられているのです。
すると多くの人が「体を休める」という選択をするので、結果的に自律神経への負担も減ります。
体の疲労感は、自律神経の防御反応と言えます。
ところが、楽しいことをしている時や、物事に意欲的に取り組んでいる時、やりがいや達成感がある時は、あまり疲れを感じません。
これは、人類の進化の過程で前頭葉が発達したことで、疲労感を消して感じないようにすることが可能になったからだそうです。
「隠れ疲労」などと呼ばれ、過労死の原因になると言われています。
自覚しにくい脳疲労に気づくには、その「サイン」を見逃さないことが大切になります。
それは・・・
続きはこちら↓
参照:日本予防医薬