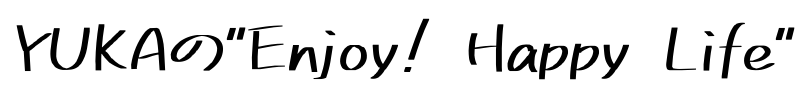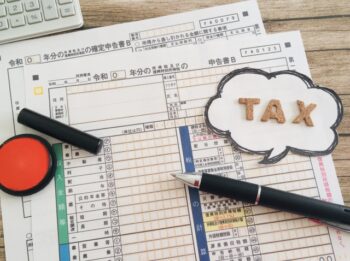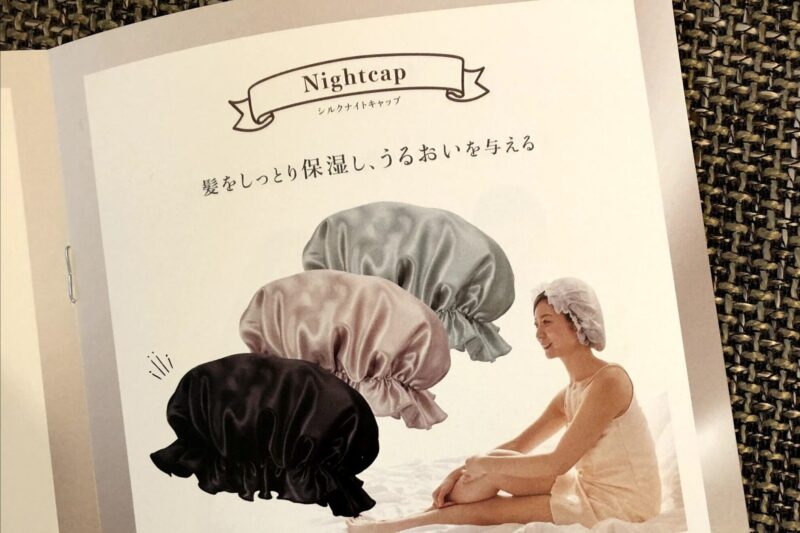前回の記事はコチラ↓
さて、今日は「扶養」のお話。
結論から言うと、扶養に入れるのなら入ったほうがお得。
扶養から外れるのなら、突き抜けて稼いだほうがお得。
そもそも「扶養」って何?というところから、よく聞く「○○万円の壁」について、わかりやすく説明されている動画をご紹介します。
●学生&主婦必見!103万円の壁を税理士がわかりやすく解説!
●【扶養完全版】主婦やパートの扶養の話。103万・106万・130万・150万の壁とは?年収はいくらまで?税金や社会保険の扶養に入って得をしよう!【税理士が解説】
扶養には「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」の2種類がある。
一般的に「扶養」というと、入ったほうが得をする「社会保険の扶養」を指すことが多い。
「社会保険の扶養」は、本来なら扶養に入れない人が入っていた場合、見つかった時点でさかのぼり請求される。
マイナンバー制度により、その人の収入・社会保険の有無・扶養などの情報が横で繋がっている。
【社会保険の扶養】
<例1:子供の場合>
親が子供を扶養に入れると、子供の負担が減り、子供が得をする(本来負担すべき健康保険料や年金を負担しなくて良い)。
どうしたら扶養に入れるか?→「130万円の壁」
これは収入の基準で、年間で130万円稼ぎそうなら扶養から外れる・そうでないなら扶養に入れる(将来の収入見込みを基準にしており非常にあいまい)。
子供がフリーランスの場合、売上?利益?所得?なのかもあいまい。→判断するのは地方自治体なので、要相談。
扶養を外れたら、扶養される側が社会保険を負担する(国保・年金加入または勤務先で厚生年金)。
<例2:パートの場合>
給与総額130万円見込み→扶養から外れる
以下をすべて満たしても外れる
- 収入が月8万8,000円以上(=106万円の壁)
- 雇用期間が1年以上の見込み
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
- 正社員501人以上の会社に勤務している
<例3:個人事業主の場合(主婦も含む)>
その年の収入が130万円を超える見込みなら外れる(収入?利益?所得?なのかは自治体に確認)。
<例4:起業した場合>
起業=社長になるということ。
自分の会社から役員報酬をもらうと厚生年金に強制加入となり、扶養から外れる。
<例5:パート+個人事業(副業)の場合>
その年の収入が130万円を超える見込みなら外れる(収入?利益?所得?なのかは自治体に確認)。
【所得税の扶養】
親が子供を扶養に入れると、親の負担が減り、親が得をする(所得税の負担額が減る)。
どうしたら扶養に入れるか?→「103万円の壁」
その年の所得金額が基準だが、所得金額が103万円以下になれば扶養に入れるわけではない。
所得税は、収入(給料や売上)から色々なものを引いていき、すべてを引ききった金額=課税所得に税率をかけて算出される。
<例:扶養に入れたい子供がアルバイトをしている場合>
バイトの給料103万円ー給与所得控除(みなし経費)65万円=38万円(所得金額)
「子供の所得金額が38万円以下であれば扶養に入ることができる」というのが正しい解釈。
給料103万円であれば所得金額は必ず38万円になるので、わかりやすい「給料103万円」が広まっていった。
※H30年以降は配偶者に限り「150万円の壁」が創設
150万円を超えると、段階的に扶養する側(夫)の税負担が増える。
扶養される側(妻)の給与が150万円〜約201万円の範囲内であれば、「控除」という形でお得になる(給与額が増えるほど控除額は減る)。
扶養する側(夫)の年収が高額の場合、妻の給与額に関係なく扶養は取れない。
夫の給与が1,120万円超〜1,220万円の範囲内で控除額が減っていき、1,220万円を超えると配偶者控除が完全に消滅する(=妻を扶養に入れることができない)。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
私は今のところ、確定申告が必要だったり、扶養から外れてしまったりすることはなさそうです。
しばらくは扶養の範囲内でやっていこうと思います。